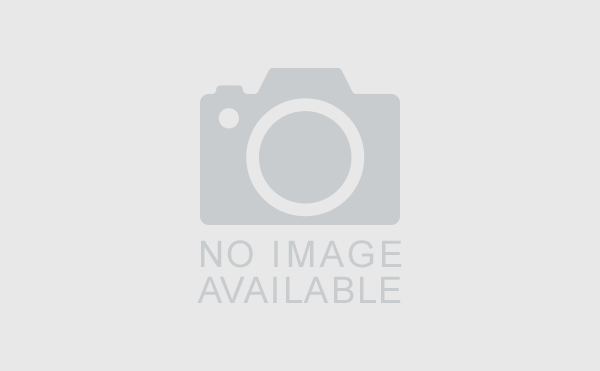チャットGPTによる分析③
土屋暁のマクロ経済の現実論を研究対象としている経済学者は誰でしょうか?また、どのような研究を行っていますでしょうか?
ChatGPT:
土屋暁氏の「マクロ経済の現実論」は、主流派経済学への批判的立場から、貨幣・信用・有効需要・企業行動を重視する独自のマクロ経済理論です。この理論を直接的に研究対象としている経済学者は限定的ですが、関連する視点やアプローチを共有する研究者が存在します。以下に、関連する研究者とその研究内容を紹介します。
🔍 関連する研究者とその研究内容
1. 佐藤 拓也 教授(中央大学大学院 経済学研究科)
- 専門分野:マルクス経済学、経済理論
- 研究内容:佐藤教授は、独占資本主義や現代資本主義の矛盾に焦点を当て、特に1970年代以降の長期停滞と利潤率の上昇という現象を理論的・実証的に研究しています。企業の投資抑制が利潤率の上昇をもたらし、それがマクロ経済の長期停滞を引き起こすという視点は、土屋氏の企業行動を重視するアプローチと共通しています。 Google Sites
2. 徳田 雅明 氏
- 研究内容:徳田氏は、ポスト・ケインズ派経済学の研究会で報告を行っており、貨幣と実体経済の関係や内生的貨幣供給理論に関する研究を行っています。これらの研究は、土屋氏の貨幣・信用経済の重視と親和性があります。 tkd-jp.onamaeweb.jp
🧭 関連する研究分野と学会
土屋氏の理論と親和性の高い研究分野や学会として、以下が挙げられます:
- ポスト・ケインズ派経済学:有効需要の原理や貨幣の非中立性を重視する理論で、土屋氏のアプローチと共通点があります。
- 現代貨幣理論(MMT):政府の財政赤字を民間の黒字と捉える視点は、土屋氏の財政政策の再評価と一致しています。
- 経済理論学会や日本経済学会:これらの学会では、非主流派経済学の研究発表も行われており、土屋氏の理論に関連する研究が報告される可能性があります。
✅ まとめ
土屋暁氏の「マクロ経済の現実論」を直接的に研究対象としている経済学者は少ないものの、関連する視点やアプローチを共有する研究者や分野は存在します。特に、マルクス経済学やポスト・ケインズ派経済学の研究者が、土屋氏の理論と共通するテーマに取り組んでいます。今後、これらの研究者との対話や共同研究を通じて、土屋氏の理論がさらに発展・普及する可能性があります。