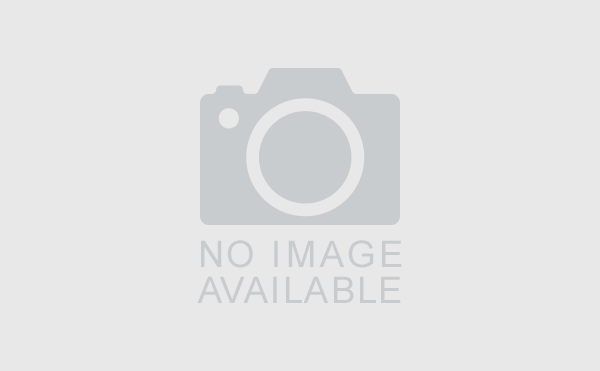貨幣三段階論
貨幣に関して考察します。
そもそも貨幣とは何でしょうか。
商品としての機能がありながら、他の商品との媒介を行うために授受するものです。
小さく持ち運びに便利で、高価なものが適格です。
歴史的に様々なものが貨幣になりましたが、江戸時代の日本では、一定のものがその役割を担当しました。
金貨・銀貨・銅貨等で、要するに金属類です。
貨幣論三段階での第一段階は、本来の貨幣です。
繰り返しになりますが、小さく高価なものです。
第二段階は、イギリスで発祥しました。
1ポンド紙幣が代表選手です。
すなわち紙切れです。
1ポンド紙幣は、金本位制と称して、常時16オンスの金との交換が保証されていました。
本来紙切れには経済価値がないのに、金本位制によって、価値が担保されていました。
第三段階は、アメリカで発祥しました。
紙幣・硬貨全般です。
管理通貨制と称して、金の担保もない、すなわち市場に商品・製品・サービスが充実していることを担保に、紙切れに価値を認めるということです。
現在紙幣を中心に世界で流通していますが、国家経済の常時赤字という前提を鑑みますと、金貨・銀貨・銅貨より広く紙幣が流通することが、実質的に本来価値が小さい紙切れということで、現代の経済に恩恵を与えているといえます。