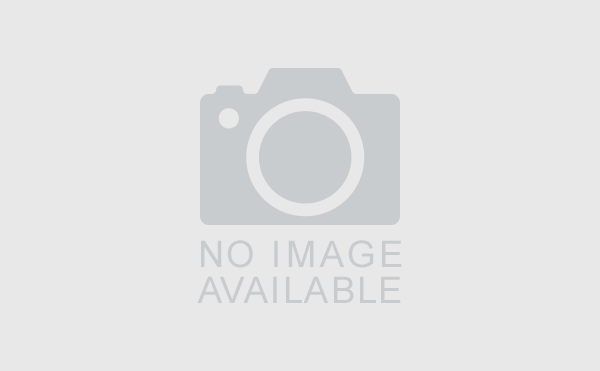トランプ関税の最終結論
トランプ関税は、アメリカからみた外国の優位な産業にやきもちを焼いて抵抗しようという動機だと推察します。
高付加価値産業・中付加価値産業・低付加価値産業と三分類してどのような結果になるかをご一緒に考察いただきます。
高付加価値産業、いわゆるノーベル賞級の研究産業が代表的ですが、応用物理・応用化学も該当しそうです。
ノーベル賞級の研究でもアメリカが比較的優位なのは、基礎研究が多くを占めています。
したがって、基礎研究は関税ゼロです。
しかし、応用物理・応用化学はどうでしょうか。日本・ドイツが比較的優位でしょうか。ここでの関税は、高額なものとなりますが、事実上そう簡単には保護貿易を行っても、アメリカの応用物理・応用化学産業は短期的には育成されず、こうした分野の物価上昇・供給不足が顕著となり、関税継続不可能です。
仮に関税継続だと、アメリカの応用物理・応用化学は、現在以上に衰退します。
中付加価値産業としては、自動車産業が代表格でしょうか。ここでは自動車産業に絞って検証します。
自動車産業は、さらに付加価値が若干低い家電産業同様、後発の国によって安い賃金でできてしまう産業にランクが下がってしまうと予想されています。
自動運転車が普及するころ、すなわち10~20年後と想定していますが、この時期にタイ・韓国等の国産車が安い賃金を背景に躍進します。
したがって、トランプ関税を自動車産業に課しても将来縮小することを前提としているため、関税を将来に渡り増額していかないとなりませんが、保護貿易を行ってもこの分野の物価上昇・供給不足に悩まされるだけです。
低付加価値産業としては、農業が代表格でしょうか。食糧自給率100%維持の観点から関税を課すことは一定の合理性がございます。
しかしながら、特段保護する目的のない分野、例えば中国の得意な機械部品の分野等で関税を課しても、アメリカでの生産がほとんどないため、物価上昇・供給不足に悩まされるだけです。
結局のところまとめとしましては、アメリカは一国だけで成り立っているわけではなく、世界各国との連携で経済的利益を享受しているため、アメリカだけが利する経済政策というものは存在しません。
保護貿易の本来の目的は、自国にとって重要な産業を、相対的に優位にある外国産業から保護して、育成することです。
したがって、育成できないのに関税を課してしまうことは、まったく不合理な政策となってしまいます。
アメリカは、トランプ大統領だけが判断するのではなく、経済論の有識者の意見も取り入れて、早期に賢明な修正の判断を行えるよう、政権体制を再整備いただきたいです。